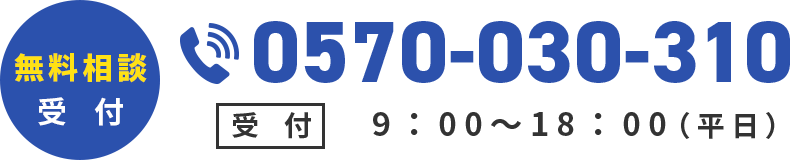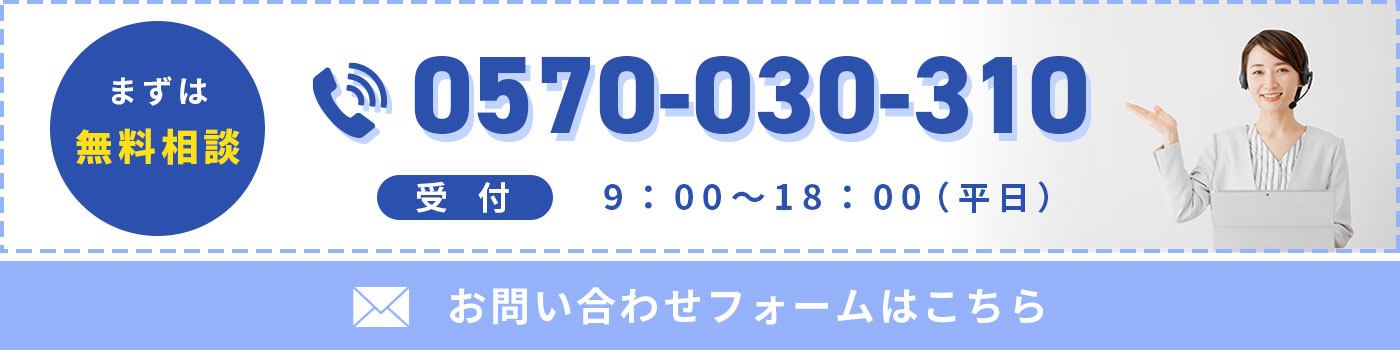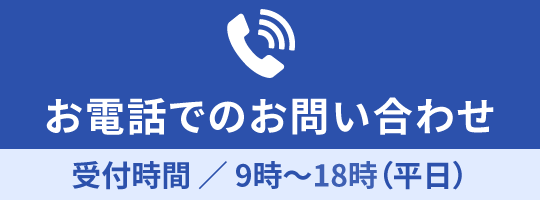北海道の豊かな自然と食文化は、国内外から多くの観光客を惹きつけ、年間延べ宿泊者数は全国トップクラスを誇ります。特にインバウンドの回復に伴い、民泊やホテル・旅館・簡易宿所などの旅館業は今、大きなビジネスチャンスとなっています。『北海道 民泊 開業』や『北海道 旅館業』といった検索ワードも増加しています。しかし、実際に民泊や旅館業の開業を進めるためには複雑な申請手続きや法律の理解が不可欠です。本記事では、北海道で民泊や旅館業を開業したい方へ、必要な許可や法規制、そして北海道独自のルールについて詳しく解説します。
1. 北海道の宿泊事業の現状と魅力
北海道の宿泊市場は、インバウンドを中心とした観光客の増加に伴い、全国でもトップクラスの宿泊地となっています。国土交通省の「宿泊旅行統計調査(PDF)」によると、令和6年の北海道の延べ宿泊者数は約4,463万人泊で、前年同期比12.6%増、全国第3位の宿泊地です。外国人延べ宿泊者数も前年同期比44.59%増とコロナ禍を経て大きく回復しています。
こうした状況から民泊や簡易宿所といった多様な宿泊形態は、北海道の季節性の強い観光需要に対応できる魅力的な手段です。冬季はニセコや富良野などのスキーリゾート地域で、夏季は札幌や函館といった主要観光地で高い稼働率を維持しており、繁忙期には90%を超えることも珍しくありません。近年はマウンテンバイクやラフティングなど夏季アクティビティを目的とする観光客も増え、民泊や簡易宿所を活用すれば、空き家や別荘を収益化できるほか、多様な宿泊スタイルで観光客に地域体験を提供できます。
一方、宿泊施設の増加により、近隣住民との騒音やゴミ出しに関するトラブル、違法営業、そして安全性確保の課題も指摘されています。こうした状況から一部地域では独自の条例を設けている場合があり、住居専用地域では年間営業日数を制限する動きも見られます。
これらの課題を乗り越え、地域の特性を理解し、単なる宿泊施設としてではなく、「体験」もあわせて提供することで、北海道での民泊運営は今後も成長が期待できるでしょう。
2. 宿泊事業を始めるための3つの手続き
日本で適切に宿泊事業を運営するためには、主に3つの法律に基づく制度から適切な形態を選ぶ必要があります。目的や手続き、運用要件が異なるため、事業計画に応じて適切な手続きを行いましょう。
・住宅宿泊事業法(民泊新法)
「民泊新法」とも呼ばれるこの法律は、民泊を始める際の最も一般的な制度です。年間営業日数が180日までに制限されますが、届け出をすることで営業が可能となり、比較的始めやすい点がメリットです。住宅宿泊事業の詳細については、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出方法と営業日数制限はこちらをご覧ください。
しかし、北海道で民泊事業を行う際には民泊新法に加え、自治体が独自に定める条例にも注意が必要です。例えば札幌市では民泊事業の届け出を行う際に防災設備に関する届出書の提出が求められるなど、他の自治体とは異なる詳細な手続きが定められています。また、近くに小中学校がある場合、敷地の出入口から半径100メートル以内では、授業のある日(平日)は営業ができませんので、必ず事前に確認しましょう。札幌市におけるルールについては札幌市HPを参考にしてください。
・旅館業法(ホテル・旅館・簡易宿所)
民泊新法での営業日数の制限を気にせず、通年で本格的な事業を行いたい場合は、旅館業法に基づく「簡易宿所」などの営業許可を取得する方法があります。ホテルや旅館と同様の許可制度のため、年間365日の運営が可能となり、より収益性の高い事業展開を目指す場合に適しています。ただし、許可取得には民泊新法より厳格な設備基準(客室面積、換気設備、衛生設備など)や消防法・建築基準法の基準を満たす必要があります。北海道で旅館業法に基づく許可申請を行う際は札幌市、函館市、旭川市、小樽市では各市保健所が、それ以外の市町村では北海道内の各振興局管轄保健所が窓口となります。また、住宅街や学校周辺に施設を設ける場合、近隣住民への配慮が必要な場合もあるため、事前確認をおすすめします。
簡易宿所に関する詳細については簡易宿所営業許可の設備要件と申請方法はこちら、旅館・ホテル営業許可については旅館業・ホテル営業許可の取得要件と関連手続きはこちらをご参考ください。
・特区民泊
「国家戦略特別区域法」に基づく制度で、特定の地域でのみ適用されます。この制度を利用すると、年間営業日数の上限がなくなり、365日運営が可能です。しかし、現在、北海道内に特区民泊の区域はありません。そのため、北海道で年間180日以上の運営を検討する場合、旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があります。また、特区民泊は最低滞在日数が2泊3日以上と定められている点も特徴です。
3. 知っておくべき宿泊事業の法律と基準
宿泊事業を安全かつ合法的に運営するためには、民泊新法や旅館業法だけではなく、その他多くの法律や基準を遵守する必要があります。
・消防法と非常用照明設備のポイント
宿泊施設は、消防法の分類や規模によって必要な設備が異なります。旅館業法で営業する場合、規模によっては「特定防火対象物」として厳格な基準が適用される場合があります。一方、民泊新法での営業でも延べ床面積や施設の構造に応じて消火器や自動火災報知設備などの設置が義務付けられることがあります。
・建築基準法における用途変更の手続き
旅館業の営業許可取得には、建物の用途(例えば「住宅」)を「旅館・ホテル」に変更する手続き(用途変更)が必要な場合があります。特に旅館・ホテルへの用途変更を行う床面積が200㎡を超える場合や、大規模な改修を行う場合は、建築確認申請を行い、建物の構造や設備が新たな用途の基準を満たしているか確認しなければならない場合があります。
・その他、宿泊事業に関連する法令
旅館業の営業許可取得には、建物の用途(例えば「住宅」)を「旅館・ホテル」に変更する手続き(用途変更)が必要な場合があります。特に旅館・ホテルへの用途変更を行う床面積が200㎡を超える場合や、大規模な改修を行う場合は、建築確認申請を行い、建物の構造や設備が新たな用途の基準を満たしているか確認しなければならない場合があります。
4. 北海道独自のルールと注意点
北海道は広大な土地を持つため、地域ごとに異なるルールや注意点が存在します。宿泊事業を始める前には、物件のある市町村のルールを必ず確認することが重要です。
・市町村ごとの条例やルール
前述の通り、北海道では多くの市町村が民泊新法に「上乗せ」する形で独自の条例を制定しています。具体的には以下のような事例があります。
・営業日数の制限:函館市など一部の自治体では、住居専用地域における民泊の営業日を土日祝日のみと限定しています。これは、住環境の保護や近隣住民の生活環境への配慮から設けられた制限です。
・学校周辺の規制:小樽市や函館市など一部の自治体では、小中学校の敷地から100メートル以内の区域での営業を禁止し、授業のある平日は営業が認めていません。
※ 自然保全地区等、独自の制限を設ける自治体もあるため、必ず事前に市町村の担当窓口へご確認ください。
旅館業法に基づく許可申請においても、各市町村が定める独自の条例(例:小樽市の「小樽市旅館業法施行条例」)や、各保健所の運用基準に従う必要があります。これらの条例では、設備の構造や衛生管理、施設の立地などについて、国の基準を上回る厳しい条件(騒音対策や防火設備の強化など)が定められている場合があります。事業計画を立てる前に、物件所在地の市町村のホームページや担当窓口に問い合わせ、詳細なルールを必ず確認しましょう。
・地域住民とのトラブルを避けるための対策
宿泊事業の運営では、騒音やゴミ出し、違法駐車など、近隣住民とのトラブルが大きな課題となりがちです。トラブルを未然に防ぐために、以下のような具体的な対策を講じましょう。
・ルールブックの作成:宿泊者に対して、ゴミの分別方法、ゴミ出しの日、騒音に関する注意点などを記載した多言語対応のルールブックを準備する。
・連絡窓口の設置:近隣住民からの問い合わせや苦情にすぐに対応できるよう、24時間対応の連絡窓口を設置し、周知しておく。
・事前の挨拶と説明:事業開始前に近隣住民へ直接挨拶し、事業内容や連絡先を伝える。
これらの対策を通じて、地域住民との良好な関係を築くことが、安定した宿泊事業運営につながります。
・届出時に必要な書類と手続きの流れ
事業形態に応じて準備すべき書類や手続きの流れが異なります。代表的な流れは以下の通りです。
・民泊新法の場合
① 事前相談:物件所在地の保健所や自治体の窓口に相談し、必要な書類や手続きについて確認します。
② 書類作成・提出:登記事項全部証明書、施設の平面図、賃貸借契約書の写し、消防法令適合通知書など、必要書類を揃えて提出します。
③ 審査・現地調査:提出された書類の審査や、消防設備の設置状況などの現地調査が行われます。
④ 届出受理:基準を満たしていれば届出が受理され、届出番号が発行されます。
・旅館業法の場合
① 事前相談:札幌市、函館市、旭川市、小樽市では各市の、それ以外の市町村では北海道立保健所に相談します。
② 書類作成・提出:申請書、施設の構造設備図、消防法令適合通知書、水質検査結果証明書など、民泊新法よりも多くの書類を提出します。
③ 審査・現地調査:書類審査に加え、設備基準や衛生管理体制が満たされているか、より厳格な現地調査が行われます。
④ 許可:基準を満たしていれば許可が下り、営業を開始できます。
必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認し、スムーズな手続きを目指しましょう。
まとめ
北海道で民泊や旅館業を成功させるには、観光客に「体験」を提供する魅力的な運営はもちろん、複雑な法律や条令を遵守することが不可欠です。まずは、物件のある市町村独自のルールを徹底的に調べることが成功の第一歩となります。宿泊事業の開業準備は、多岐にわたる手続きや書類作成が必要です。SATO行政書士法人では、こうした複雑な手続きを全国対応でサポートし、お客様が安心して開業できるお手伝いをいたします。開業準備や許可申請に関するご不明点は、ぜひ下記URLよりお気軽にお問い合わせください。
SATO行政書士法人では民泊に関するご相談や申請のサポートを行っております。スムーズな申請や活用のための提案などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら↓
https://sato-minpaku.com/inquiry/